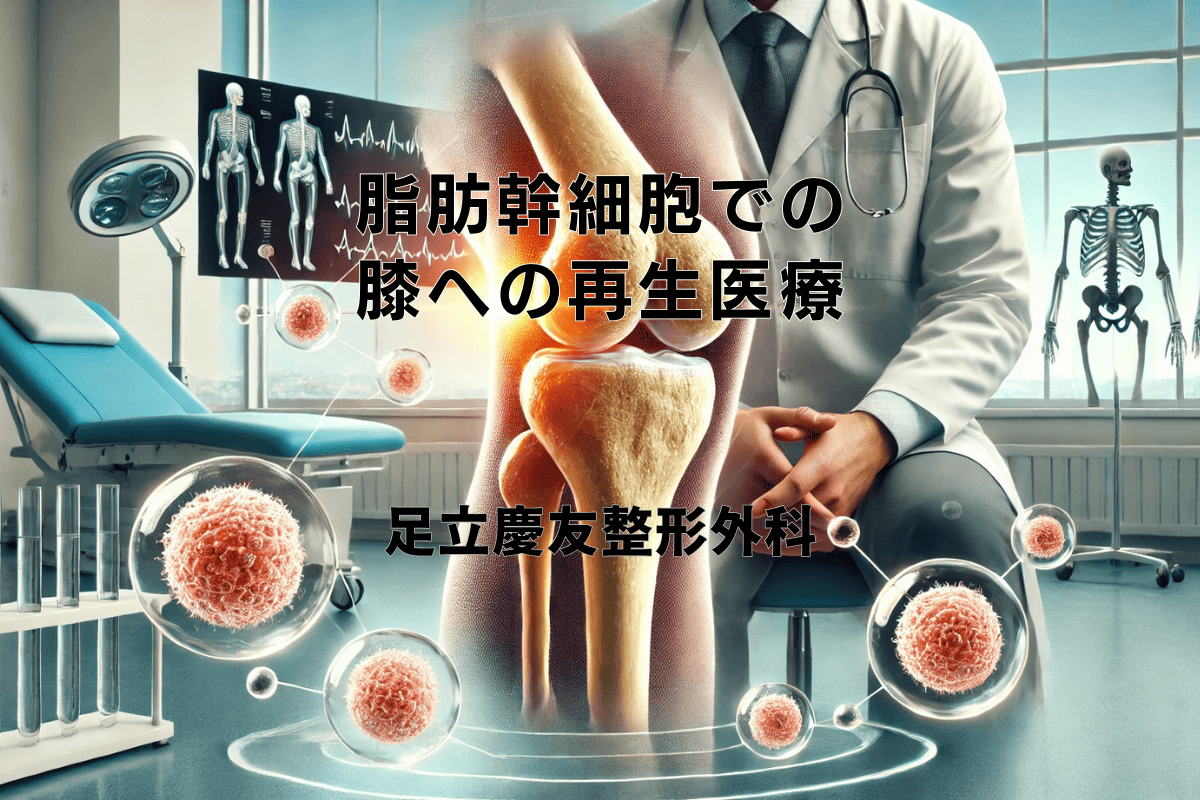
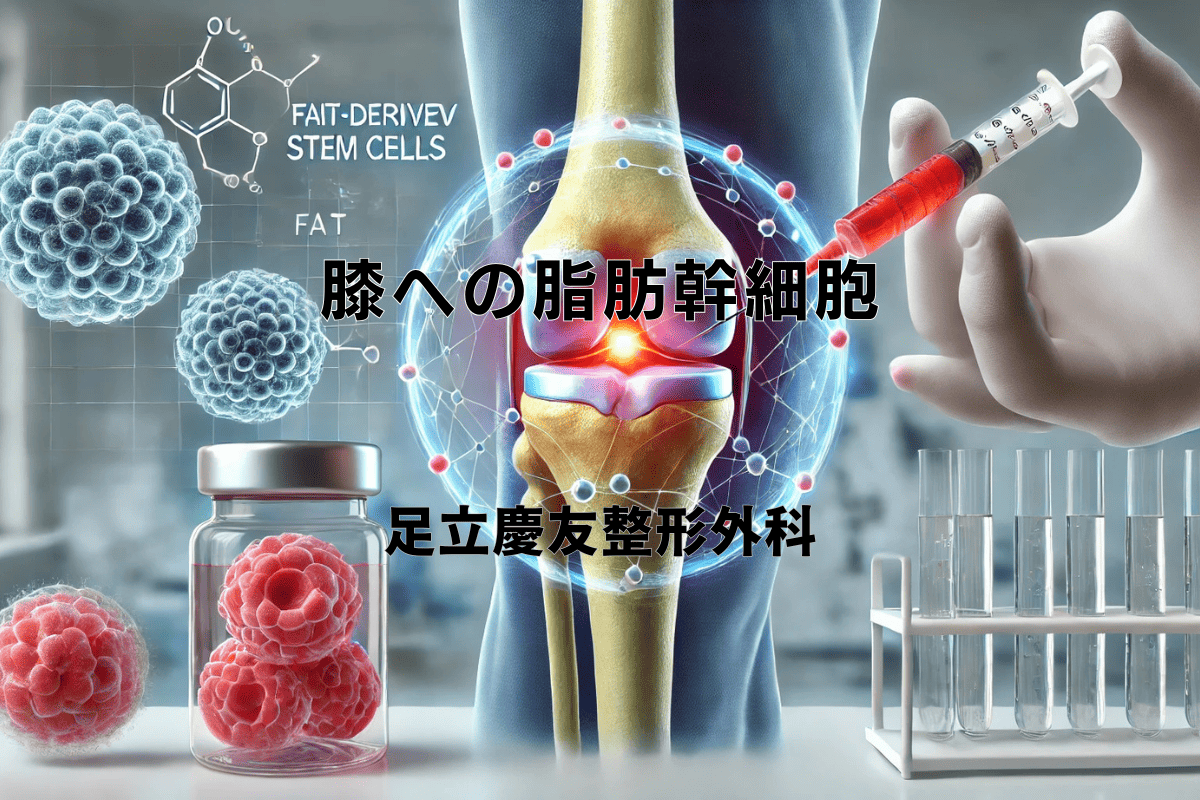
膝の痛みが続くと、歩行や日常生活にも支障が出て不安になるかもしれません。
近年、脂肪幹細胞を利用した再生医療が注目を集めています。患者自身の脂肪から幹細胞を採取し、培養して注射などで患部に投与する方法で、炎症を抑えたり軟骨の保護をめざしたりします。
本記事では、脂肪幹細胞膝治療の具体的なメリットや治療の流れ、費用面、専門医療機関の選び方などを詳しく解説します。
将来的に手術を回避したい、痛みを軽減したいと感じる方の参考になれば幸いです。
膝関節の痛みや炎症は、変形性膝関節症をはじめとするさまざまな症状に結びつきます。
近年、患者自身の脂肪から幹細胞を取り出して培養し、患部に投与する幹細胞治療が再生医療の一環として期待を集めています。治療の安全性や効果を知ることはとても大切です。
脂肪幹細胞は骨髄由来の幹細胞に比べて採取が容易で、患者自身の細胞を使うため拒絶反応が少ないことが魅力です。
主に下腹部や大腿部などから少量の脂肪を採取し、そこに含まれる幹細胞を取り出して増殖・加工します。
投与された幹細胞は炎症を鎮め、軟骨再生のサポートを行う可能性があります。
実際には軟骨が劇的に再生するというよりも、症状を改善させたり機能を保ったりする事例が報告されており、痛みの緩和が期待できます。
膝の関節軟骨がすり減って発症する変形性膝関節症は、高齢者に多い疾患です。脂肪幹細胞治療は、痛みを緩和して関節の炎症を抑える効果がある程度報告されています。
手術以外の選択肢を探している方にとって有力な候補となります。
| 主な目的 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 痛みの軽減 | 幹細胞が炎症物質を抑制し、痛みを緩和する可能性がある |
| 炎症抑制 | 投与された幹細胞が免疫調整に働きかける |
| 関節機能の維持 | 軟骨の破壊を抑え、変形の進行を遅らせる |
| 生活の質向上 | 手術を避けながら膝の状態を保ち、歩行能力を保つ |
自家脂肪由来の間葉系幹細胞は、体内の損傷部位に対して保護的な働きをするといわれています。
このセクションでは脂肪幹細胞が持つ性質と、膝治療への適応が注目される理由を解説します。
骨髄にも間葉系幹細胞は存在しますが、骨髄穿刺による採取は痛みや負担が大きくなることがあります。
一方、脂肪由来幹細胞は採取部位に皮膚の小切開などが必要になりますが、比較的負担が少ないとされています。
脂肪由来幹細胞は増殖能が高く、わずかな脂肪組織から多くの幹細胞を得られる可能性があります。この増殖力の高さが、培養を通じて必要な細胞数を確保する上で重要です。
| 比較項目 | 脂肪由来幹細胞 | 骨髄由来幹細胞 |
|---|---|---|
| 採取のしやすさ | 脂肪吸引で行う | 骨髄穿刺が必要 |
| 採取時の痛み | 比較的少ない | やや大きい場合がある |
| 増殖速度 | 高め | やや低め |
| 拒絶反応 | 自家細胞のため少ない | 自家細胞のため少ない |
| 主な用途 | 関節疾患、慢性疼痛など | 血液疾患を含む幅広い分野など |
膝の再生医療として幹細胞治療を受けるには、診療や検査、採取、培養、投与のステップがあります。ここでは一般的な流れと注意点を紹介します。
患者はクリニックで初診や問診を受け、膝の痛みや症状の程度を確認します。レントゲンやMRIなどの検査を行い、変形性膝関節症などの診断を確定します。
腹部や大腿部などから局所麻酔を用いて脂肪を採取します。採取量は個人差がありますが、治療に必要な量を少し余裕をもって採取することが多いです。
採取後は包帯やテープで軽く圧迫し、出血や腫れを抑えます。
採取した脂肪組織から間葉系幹細胞を分離し、専用の培養施設で細胞数を増やします。培養期間は数週間かかる場合が多いです。
十分な細胞数を確保した後は必要に応じて細胞を凍結保存することもあります。
培養を終えた幹細胞を膝関節に注射します。注射はクリニックの治療室で行い、施術後は安静にしてから帰宅するケースが一般的です。
術後しばらくは患部に負担をかけすぎないように注意が必要です。
| 項目 | 投与前 | 投与後 |
|---|---|---|
| 準備 | 脂肪採取・培養 | 注射用細胞の最終確認 |
| 施術 | ローカル麻酔での脂肪吸引 | 膝関節内への幹細胞注射 |
| 入院の必要性 | 通常は不要 | 当日または翌日に帰宅可能 |
| 術後のケア | 採取部位の圧迫や保護 | 安静を中心にリハビリ・負担調整を行う |
投与後、定期的に診察を受け、膝の痛みや可動域の変化を評価します。必要に応じてMRIやレントゲン検査を行い、改善の度合いを確認することもあります。
脂肪幹細胞による膝の幹細胞治療は、多くの場合、自由診療(保険適用外)となります。そのため、保険診療とは異なる費用負担が発生します。
クリニックや施設によって料金は大きく異なります。おおむね数十万円から数百万円の幅があり、投与回数や培養の有無によって変動します。
自由診療のため、一括払いが難しい場合に分割や医療ローンを利用できる医療機関もあります。事前に予約時などに確認しておくと安心です。
現時点では、変形性膝関節症に対する脂肪幹細胞治療は保険診療の枠組みに入っていません。
しかし一部の検査やリハビリ、投薬などは保険で受けられる場合もあるので、クリニックで相談すると良いでしょう。
| 内容 | 目安費用 (例) | 備考 |
|---|---|---|
| 初診・検査 | 1万円~3万円程度 | 画像検査や診察費など |
| 脂肪採取・培養 | 30万円~80万円程度 | 採取量や回数、培養プロセスにより変動 |
| 幹細胞注射1回 | 10万円~30万円程度 | 投与回数によって総額が増加 |
| 分割払いの可否 | 医療ローン対応施設あり | 事前に問い合わせが必要 |
脂肪幹細胞を用いる膝の再生医療は、さまざまな研究や症例報告が増えてきました。メリットとともにリスクや注意点もあります。
投与された幹細胞が炎症を抑える作用を発揮し、痛みの軽減に寄与することが期待されます。数か月から半年程度経過した段階で、効果を実感する方も多いと報告されています。
変形性膝関節症では軟骨がすり減っていきますが、幹細胞治療は軟骨の破壊を遅らせたり保護したりする可能性があります。
全くの再生までは難しい場合もありますが、進行を緩和する役割が期待されます。
効果をより長く維持するには、術後も定期的な診察を受け、運動療法や生活習慣の改善に取り組むことが大切です。膝への負担を極力減らし、再発を防ぐ工夫が求められます。
手術が適応とされる進行度の高い変形性膝関節症でも、入院や人工関節置換を避けたい方は少なくありません。脂肪幹細胞治療は、手術より負担が少ない選択肢として考えられます。
ヒアルロン酸注射やリハビリテーションなどの保存療法と比べて、根本的な炎症抑制や組織保護作用が期待できます。
従来の保存療法で効果が十分得られなかった方が新たに選択するケースが増えています。
人工関節置換は進行した変形性膝関節症に対する有効な治療法ですが、入院やリハビリ期間が長くなるリスクがあります。
脂肪幹細胞治療は手術を要しないため、通院で施術を終えられる利点があります。
幹細胞治療を受けた後も、過度な肥満や運動不足があると症状が再発・悪化することがあります。生活習慣の見直しやリハビリを継続し、膝の負担を減らす取り組みが必要です。
専門医の診察を受け、自身の症状や生活スタイル、将来の見通しに合わせて治療法を検討するのがおすすめです。カウンセリングでしっかり相談すると安心です。
| 項目 | 保存療法 | 人工関節置換 | 幹細胞治療 |
|---|---|---|---|
| 治療内容 | リハビリ、注射、内服薬など | 人工関節を設置する外科手術 | 自家脂肪幹細胞の培養・注射 |
| 身体への負担 | 比較的少ない | 大きい | 中程度(採取・注射) |
| 入院の必要性 | 通院で可能 | 通常2週間前後 | 原則不要 |
| 期待できる改善効果 | 痛み緩和だが根本治療ではない | 痛みの根本解消 | 痛み軽減や軟骨保護 |
| 手術リスク | なし | 感染、血栓など | 採取部位や注射部位の感染 |
| 費用 | 保険適用で低額 | 保険適用(一部自己負担有) | 自費診療で高額になる場合あり |
幹細胞治療はまだ広く保険適用されていないため、ランダム化比較試験のデータは限定的です。
しかしながら、小規模な臨床研究や報告で、症状の改善や日常生活への支障が軽減したケースが複数見られます。
日本では再生医療安全性確保のために、第3種再生医療などの承認を受けて治療を提供している施設が増えています。海外ではアスリートが軟骨修復をめざして利用する例もあります。
症状や年齢、体質、生活習慣により治療効果は異なります。数字だけでなく、治療後の生活スタイルやリハビリの継続が改善度合いを左右します。
さらなる大規模研究や長期的なフォローアップのデータ蓄積が進められており、今後の知見の拡大が期待されています。
膝の幹細胞治療では、投与後のリハビリや日常生活の調整がとても大切です。回復効果を高め、痛みの再発を防ぐためにもポイントを押さえておきましょう。
膝を動かさないでいると関節まわりの筋力が低下し、痛みや変形が進むリスクがあります。ウォーキングや軽いストレッチで筋力と柔軟性を保つよう心がけます。
幹細胞治療を受けた後も、定期検診で膝の状態をチェックします。必要に応じて追加の注射やリハビリメニューの見直しを行い、長期的な改善をめざします。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 運動の頻度 | 週2~3回程度から開始し、状態に応じて調整 |
| 負荷量 | 痛みを感じる手前で止め、徐々に強度を上げる |
| 呼吸の合わせ方 | 息を止めずに一定のリズムで行う |
| 痛みが出たときの対処 | 無理せず休憩し、必要に応じて医師に相談 |
膝の脂肪幹細胞治療に関して、患者からよく寄せられる質問をまとめます。治療を検討する際のヒントにしていただければ幸いです。
個人差がありますが、3か月ほどで痛みの軽減を感じる方が多いです。半年~1年かけて徐々に関節機能が改善するケースもあります。
多くの場合、高齢者でも受けることが可能です。ただし、重度の合併症や重篤な既往症がある場合は注意が必要なので、医師と相談して判断します。
クリニックの方針や培養の仕組みにより異なります。脂肪組織を1回採取して2回分の投与に備えるところもあれば、症状に応じて追加の採取や注射を行うところもあります。
ヒアルロン酸注射やリハビリテーションなどと併用するケースもありますが、治療間隔や投与タイミングには留意が必要です。医師の指示を仰ぎましょう。
膝の脂肪幹細胞治療を検討する際は、医療施設の設備や専門性にも注目してください。培養施設をしっかり備えたクリニックや安全対策が整った病院を選ぶことが重要です。
再生医療に精通した整形外科専門医やスタッフが診療にあたります。患者1人ひとりに合わせた治療計画を提案し、きめ細やかなフォローアップを行う体制をとっています。
症状が重度の場合は、手術を専門に行う医療機関と連携して必要な治療を提案します。患者の状態に合った最善の方法を総合的に検討する方針を取っています。
| 取り組み | ポイント |
|---|---|
| 安全な治療環境 | 無菌操作や厳格な品質管理 |
| 個別最適化された治療計画 | 患者の症状や生活習慣に合わせたオーダーメイドの治療 |
| 治療後のフォローアップ | 定期診察やリハビリ指導で継続的なサポート |
| 院内外の医療連携 | 必要に応じて他の専門医や医療機関と連携 |
初めて膝の幹細胞治療を知った方は、どのように進めれば良いのか戸惑うかもしれません。当クリニックの例を参考に、一般的な流れをイメージしてみてください。
電話やWEB予約で受診予約を行い、来院時に医師と症状や生活スタイルなどを相談します。診察と画像検査によって膝の状態を把握します。
治療の適応がある場合、費用や期間を含めて説明を受け、同意いただいた上で治療契約を行います。脂肪採取の日程などもここで調整します。
下腹部などから脂肪を採取し、検体を培養施設にて幹細胞を増やします。複数回投与を想定する場合は、細胞を部分的に凍結保存する場合があります。
膝への幹細胞注射を行い、数時間の安静後に帰宅できます。翌日や1週間後、1か月後などに再診し、痛みの程度や腫れがないかをチェックします。
| ステップ | 所要期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 初診・検査 | 1日 (通院) | レントゲン・MRIなどで状態を確認 |
| 脂肪採取 | 1日 (通院) | 局所麻酔下で脂肪を吸引 |
| 培養 | 約4~6週間 | 必要な細胞数まで増殖・加工 |
| 幹細胞注射 | 1日 (通院) | 膝関節内に注入、当日または翌日帰宅可能 |
| 経過観察 | 数か月~1年単位 | 必要に応じて検診やリハビリを継続 |
膝の幹細胞治療だけではなく、食事や運動、睡眠といった基本的な生活習慣の見直しも必要です。膝への負担を減らし、治療効果を長続きさせるために注意しましょう。
体重が増えると膝にかかる負荷が増し、軟骨の摩耗を加速させるリスクがあります。適正体重を維持することが、膝の痛み軽減には欠かせません。
軟骨や筋肉の維持には、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどバランスのとれた栄養が欠かせません。過度な糖質・脂質摂取を避け、野菜や果物などを適度に取り入れましょう。
歩行や軽い筋トレ、水中運動などで膝まわりの筋肉を強化し、関節を安定させます。ただし無理な負荷や長時間の運動は逆効果となることがあるため、専門家のアドバイスを参考にしてください。
炎症が起きているときは過度な動きがかえって症状を悪化させることがあります。休養を適度に取り、睡眠時間を確保して自然治癒力を引き出すように心がけます。
脂肪幹細胞を活用した膝の幹細胞治療は、手術に抵抗がある方や保存療法に満足できなかった方にとって、新たな選択肢となり得ます。
実際の効果やリスクは個人差がありますが、軟骨の保護や痛みの軽減に一定の報告があり、研究も増えています。
大切なのは患者自身が治療法を正しく理解し、医療機関の指示を守り、適切な運動や生活習慣の改善を並行して行うことです。
膝の痛みを軽減し、生活の質を高めるために、医師や専門スタッフと二人三脚で取り組んでいきましょう。
以上
BIAZZO, Alessio, et al. Autologous adipose stem cell therapy for knee osteoarthritis: where are we now?. The Physician and Sportsmedicine, 2020, 48.4: 392-399.
FREITAG, Julien, et al. Adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Regenerative medicine, 2019, 14.3: 213-230.
KOH, Yong-Gon, et al. Clinical results and second-look arthroscopic findings after treatment with adipose-derived stem cells for knee osteoarthritis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2015, 23: 1308-1316.
CHANG, Jun, et al. Systemic and local adipose tissue in knee osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage, 2018, 26.7: 864-871.
USUELLI, Federico Giuseppe, et al. Adipose-derived stem cells in orthopaedic pathologies. British Medical Bulletin, 2017, 124.1: 31-54.
VAN PHAM, Phuc, et al. Symptomatic knee osteoarthritis treatment using autologous adipose derived stem cells and platelet-rich plasma: a clinical study. Biomedical Research and Therapy, 2014, 1: 1-7.
LEE, Woo-Suk, et al. Intra-articular injection of autologous adipose tissue-derived mesenchymal stem cells for the treatment of knee osteoarthritis: a phase IIb, randomized, placebo-controlled clinical trial. Stem cells translational medicine, 2019, 8.6: 504-511.
SPASOVSKI, Duško, et al. Intra‐articular injection of autologous adipose‐derived mesenchymal stem cells in the treatment of knee osteoarthritis. The journal of gene medicine, 2018, 20.1: e3002.
SCHIAVONE PANNI, Alfredo, et al. Preliminary results of autologous adipose-derived stem cells in early knee osteoarthritis: identification of a subpopulation with greater response. International orthopaedics, 2019, 43: 7-13.
CHEN, Cheng-Fong, et al. Treatment of knee osteoarthritis with intra-articular injection of allogeneic adipose-derived stem cells (ADSCs) ELIXCYTE®: a phase I/II, randomized, active-control, single-blind, multiple-center clinical trial. Stem Cell Research & Therapy, 2021, 12: 1-12.
膝の痛みのお悩み、医療の不安は、
まずはご相談ください。

膝・関節の治療実績多数
整形外科の専門医がご対応
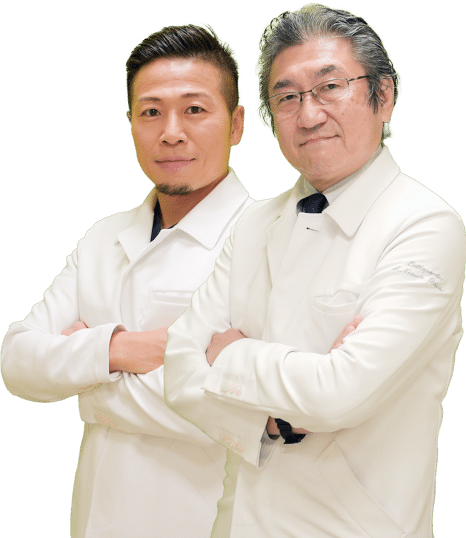

電話で相談・来院予約
「ヒザの痛みで相談」と電話ください